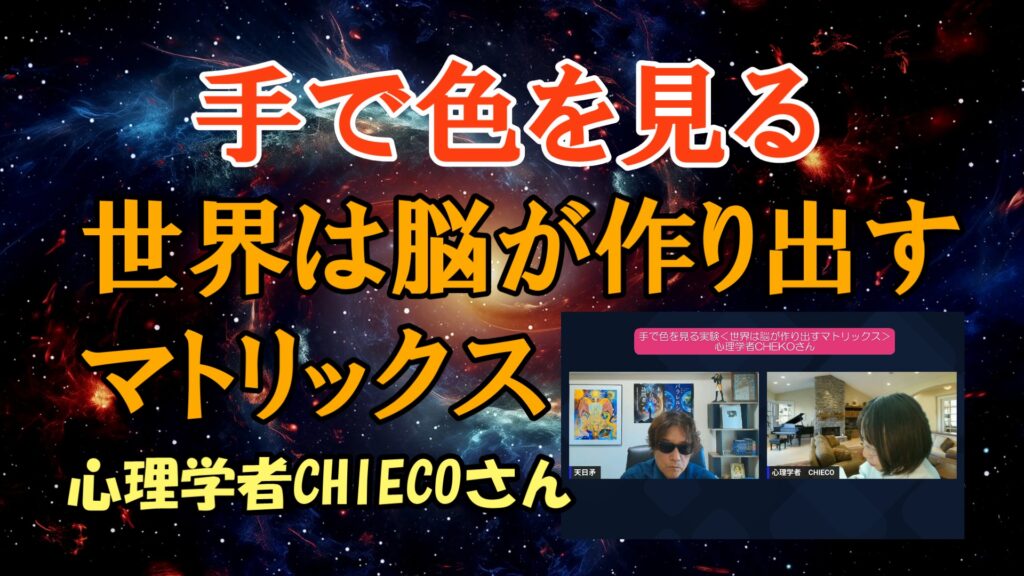手で色を見る<世界は脳が作り出すマトリックス>
皆さん、こんにちは。
今回は、またまた素晴らしいゲストをお呼びしています。
心理学者のCHIECOさんです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
私はいつも日矛さんの動画を拝見させていただいていまして、とても面白い動画がたくさんあるんですけれども・・・。
何よりも私が1番感動したポイントは、日矛さんがとても思いやりのあるやり取りをされているというところなんですよね。
見た方によっては、少し強面なんじゃないかという風に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、言葉のやり取りの細かさを拝見していると、とても繊細で配慮の行き届いた方だなと、とても私は感動しております。
前に少しお話をさせていただいた時にも、やはり思った通りの方だなと思い、今日は本当に楽しみにしていました。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
では、私の方からCHIECOさんについて少しご紹介しますね。
心理学者CHIECO
医学博士、公認心理師、臨床心理士。
30年以上に渡り病院、教育、大学、研究所などで生理学的実験研究や心理臨床研究に携わり、大学教授を務める。
ストレス、愛着問題、HSPなどの臨床・研究や、人間性心理学・トランスパーソナル心理学などを研究。
ということで、これだけでもすごく私のチャンネルにぴったりの、本格的な方にご登壇いただくことができたということで、私も今日は楽しみにしています。
よろしくお願いします。
では、CHIECOさんの方から簡単に自己紹介をお願いします。
心理学者をしておりますCHIECOと申します。
実験心理学から臨床心理学の科学まで、割と幅広く研究に携わらせてきていただいております。
今回は、そういったことの研究、あるいは経験からお話をさせていただけたらと思っております。
では、早速本題に入りたいと思います。
今回取り扱うテーマは、非常に深い内容になっていますので、2 話に区切ってお話していきます。
今日は、その第1話ということですね。
スピリチュアルや都市伝説の類の話で、「この現実世界は脳が作っている幻想に過ぎない」ということがよく言われますよね。
よくイーロンマスクなども、そういうことを言っていますし、映画「マトリックス」の世界は、まさしく脳が世界を構築しているということを表現しています。
そういう風に、それが普通に、まことしやかに言われているんですけれども・・・。
実は実験心理学の研究でも、それが明らかになっているとしたら、これは非常に面白い話 ですよね。
そういうことで順に、CHIECOさんがどういう実験をされているかということを、お話ししていきたいと思います。
では、よろしくお願いします。
●超ひも理論を脳生理学から説明できるのでは
はい 。
早速なんですが、「脳がこの世界を作っているのではないか」という超ひも理論とも言われるその現象を、脳生理学から説明できるのではないか、あるいは実験心理学的な観点から説明できるのではないかということについて、今回私が研究をした結果のことから説明していきたいと思います。
●手で色を見る
皆さんは、手で色を見たことがあるでしょうか?
あるいは感じたことがあるでしょうか?
手で色を・・・ですか?
色というのは、普通は視覚的に目で見るものですけれども、手で色を見るとは?
そうですね。なかなかない質問かもしれません。
人は、それができるとわかっていたら挑戦するんでしょうが、できるかどうかわからないことを、なかなかやらないんですよね。
だから初めてお聞きになった方も多いかと思います。
私がこの研究を始めたきっかけというのは、最初色カードで遊んでいたんですね。
そして、「あれ、なんか手で色がわかるかもしれない」ということを感じたんです。でも「これは私だけなのか、みんながそう感じているのか、どうなんだろう?」と思っていたんですね。
そうしたところに、ある皮膚科学の実験結果というのを目にしたんですね。
それが、「皮膚は色を感知している」という結果だったんです。そして、それはすでにもう皮膚科学の中では常識になっていて、いろんな皮膚治療行為に使われているんですね。応用されています。
今、日本人がLEDの発明によって、光にいろんな色をつけることができるようになり、その器具が色々販売されているんですね。だから皮膚科の中で使われるだけではなく、もうすでに美顔器として一般に販売されています。
例えばAmazonとか楽天などを少し検索していただくとわかると思うんですけれども、そういった機器の中のある種の効能として、例えば赤と青の光というのは、シミとか皺の治療に効果的であるということがわかっています。
私たちの目の網膜にあるオプシンの一種であるロドプシンと呼ばれる光を感じる物質があるんですが、それが手の皮膚の中にもあるんだということがわかっているからなんですね。
ところが、物に色はないということも一方でわかっているんです。
「いや、物に色はあるでしょう。りんごは赤だと見えるじゃない」と思うかもしれないんですが、これは光が物にあたって、吸収された光は物の中に入っていくんですけれども、それ以外の部分が反射されて目の方に入っていくので、その周波数を脳がキャッチして赤であるとか黄色であるという風に知覚しているんですね。
人はそのようにりんごを赤という風に知覚するんですけれども、生物によって色の知覚の仕方は違っているということもわかっているんです。例えばモンシロチョウは、赤は見えないんですね。だからりんごを赤とは多分わかっていないんです。そう感じていないんですね。
ところが青とか緑、あるいは紫外線は感知でき、それは見えているということなんですね。紫外線が見えるのは、少し羨ましいなと私は思ったんですね。というのは、女性としては今日は紫外線が強いぞとか、あるいはパソコンやスマホから紫外線が出ていると思ったら、UVケアして気をつけようという風に思えるかな、と思ったんですよね。
このモンシロチョウに関しては、おそらく紫外線を見ることによって仲間のモンシロチョウがオスかメスかの判別をしているということですよね。
ここまでのところで私が思ったのは、モンシロチョウが赤が見えない理由は、きっと赤を見る必要がないからですよね。
●生物は生命維持活動をする上で必要な情報をキャッチしている
おそらく、生物が生命維持活動をする上で、必要にかられた情報を自分でキャッチする、ということで紫外線は見えるけれども赤は見えない。
それを考えた時に、人間の目も必要に応じたところの領域が見えているということなのかなと思いました。
必要がそこを発展させるという説は、確かにありますね。おっしゃる通りだと思います。
さて色の概念の他にも、物においても特異的な知覚の細胞が働くということが言われています。
例えば老婆細胞仮説というのがあります。
これは自分のおばあさんを見た時だけに、特異的に活動する単一または少数の細胞が存在していて、おばあさんを見た時に「あっ、おばあさんがいる」と、それらの特異的な細胞が活性化されるんですね。
あるいはりんご特有の細胞があって、それが活性化されて「あっ、りんごがある」という風に知覚する。
さらには赤という色に関しても、赤いものに対応した細胞が活性化して「赤」という風に知覚していると考えられる、ということなんですね。
●脳の活性化は学習による
今言われた老婆細胞というのは、多分心理学用語なんだと思うんですが、要するに日頃一緒に生活している自分のおばあちゃんを見たとしたら、おばあちゃんであるという認識は他人とは違うので、一瞬にしてそれがわかるということですよね。
そういう風にして学習することによって、それが活性化するということなんでしょうか?学習の領域に入っていくのかなと思ったんですけれども、どうでしょうか?
そうですね。
おっしゃる通りある程度学習をしないと、それは知覚として結びつかない、神経として結びつかないということにはなると思います。
例えば、生まれ立ての赤ん坊はよく目が見えないという風に俗説で言われるんですけれども、目が見えないのではなくて、視覚の細胞はちゃんと整っているんですが、学習していないからなんですよね。
世界を見るという学習が出来上がっていないから、見えていないかのように大人から見たらそう思ってしまう、ということかなと思ったんですけれども・・・。
その可能性は十分あると思います。
そして、感覚と知覚というのは違うプロセスだというお話をしていきたいと思います。
つまり先ほど、皮膚科学において皮膚は青であるとか赤であるという風に、感覚としてわかることができるというお話をしましたけれども、それが脳の方に伝わって、これは青であるとかこれは赤だという風にわかるというのは、また違う神経のプロセスなんですね。
今回そこで実験としては、色の知覚力は練習により向上するのか、つまり青を触った時に「これは青だ」と言えるように人間はなるのか、ということを実験で調べました。
もちろん実験で証明できたからと言って、ただの現象論に過ぎなくなってしまうんですが、それを分子生物学レベル、生理学レベルと順を追って証明することによって、きちんと学術的に認められるということなんですね。
今回、イギリスの学術ジャーナルにこの研究が掲載されまして、一応認められたということになりました。
その実験なんですが、まず命題として皮膚は色を感知する。そして、皮膚は色を感知した時に脳波もそれに応じて変化する、ということから人は手の皮膚で色を知覚できるかということを、2つの実験で確認しました。
実験1では、220人の健常者の方にご協力いただいて、色カードの識別ができるかを実験しました。
実験2では、2人の全盲の方、そのうち1人は誕生時より全盲でした。そしてもう1人の方は11歳まで健常者で、その後全盲になられて、実験当時50代だった方です。その方々に同じ実験をしてもらったんですね。
その結果、実験1の健常者のものにおいては、比較群、つまり練習しなかった群に比べて1ヶ月の練習で統計的に有意に色の識別率が向上しました。
実験2の全盲者の実験においては、11歳まで健常者だった全盲者の方においてのみ、1ヶ月の練習後、統計的に有意に色の識別率が向上しました。
つまり視覚経験と色の知覚ということが関係しているのではないか、という風に考えられると思います。
人生の途中で全盲となった人の方が皮膚の色の識別率が高かったことから、視覚経験により、やはり色の概念が脳で出来上がるのかもしれません。
もちろんこの実験は、もっと多くの全盲者の方たちにご協力いただいて、追試実験をする必要があると思いますが、今のこの段階での研究では、このようなことが推察されるかと思います。
そして皆さんも、もしかしたら練習により手で色を識別できるようになるかもしれませんので、是非試してみましょう、ということを申し上げたいです。
人は練習次第で色を知覚することができる、という実験ですね。眼球ではなく、手でそれを感じ取ることができるだろうという仮説を立てて、それが実験でもそうなったという話ですよね。
それで確認ですけれども、人生の途中で全盲になった人の方が識別率が普通の人よりも優っている、ということも言えるのでしょうか?
その可能性が高いということですね。
もちろん今回の実験は2 人だけなので、もっと追試実験をする必要あると思うんですが、今回の実験からはそのようなことが言えるかと思います。
●一つの機能が失われると他の機能がそれを補う
映画「座頭市」で、座頭市が聴力が異様に発達していて、普通の人が感じないようなサイコロの音みたいなものを拾って、何の目が出るかがわかるというような話がありました。
あれは映画の世界ですけれども、座頭市の場合、視覚を失っているから特化して聴覚を研ぎすませ、自分が持っていないものを、他のもので補っているんですね。
ベートーベンが、聴覚を失った後に骨伝導で音を拾ったという有名な話もありますよね。それとよく似た感覚で、元々全盲に近い人が、実は手を使って色を感じ取ることもできるのかもしれないということですね。
つまり、我々が五感で聴覚とか視覚とか一般的に思っているものは、実はもっと守備範囲がすごくオーバーラップしている、ということなんでしょうか。そういう風に感じました。
そうですね。
今の座頭市さんのお話と似た話なんですけれども、1つの機能が失われると他の機能が補うように伸びる、という現象はよくあります。
例えば今回、いろんな全盲の方が実験にいらっしゃったんですが、1ヶ月の練習まで付き合っていただいた方は少なかったので、このような実験結果になったんですね。
でも、お会いした方は最初はもっと多かったんですね。
その際に私がびっくりしたのが、ほとんどの全盲の方たちは、何かしらの天才的な能力を持っていらっしゃるということです。
例えばスマホに書かれている文章などを、速聴で読まれるんですね。それが10倍速ぐらいの速さで読まれるんですよ。もう何を言っているか、私にはさっぱりわからないんです。ただ電子音みたいな音が聞こえてくるだけなんですね。
他にも楽器を本当にすごいレベルで弾ける方もいらっしゃいました。
●脳が学習することにとって概念を作り出している
要は脳が学習することによって、概念を作り出しているということですよね。
そうですね。
視覚経験により、色の概念が脳で出来上がるという順番ですよね。
最初に色の概念があって、それを脳で受け取るんではなくて、視覚経験をするということによって色の概念が作られる。だからこそ、手で触ってその色がわかるということも極論を言ったらできるんだ、という話ですよね。
視覚経験により、色の概念が脳でできるのかもしれない、ということなんですけども、もう少し詳しくご説明いただいていいですか?
はい。
脳の中で「これが赤色である」とか、「黄色である」というのを、子供時代にいろんな経験を積んで学んでいくんですね。
クレヨンを用いて絵を描いたり、触れたりすることによって、「自分は今、赤を見ているんだ」とか、「青を見ているんだ」という風に脳が学習していって、その概念が出来上がっていくという風に考えられるんですね。
つまりその色に特異的な神経細胞が活性化され繋がっていく、という感じでしょうか。
●脳は世界を構築しているマトリックス
ありがとうございます。
ここまでのところで、視覚経験と色の知覚実験について色々とお話を伺っていったんですけれども・・・。
この実験を総合してそのエッセンスを取り込んだ時に、最初のところに立ち返ると、脳がどうも世界を構築しているマトリックスであるというところに、どういう風に結びつけていけばいいのでしょうか?
はい。
結局私たちが感じているのは、全て周波数なんじゃないか。つまり色にしても周波数で、特異的な周波数を赤という風にネーミングしていたり、青という風に私たちはネーミングしていたりするわけです。
音にしても周波数で、物にしても、目の前にある鉛筆やパソコンなどというものにしても、実は全部周波数からなっていて、それが固形だという風に私たちが感じているに過ぎない 。皮膚がそういう風に触って感じているといったものにすぎないのではないか、という風な考え方があるんですね。
これを「超ひも理論」という風に、物理の世界では言うと思うんですが・・・。
超ひも理論(超弦理論)
超ひも理論は、現代物理学の理論の1つで、物質の最小単位である素粒子は、実際には大きさが無限に小さい点ではなく、1次元の広がりを持つ「ひも」のようなものであると考える理論。
この「ひも」が振動することで、様々な素粒子や力が生まれると考えられている。
私たちの脳が幻想という世界を作っているのであれば、結局一喜一憂しているのは、あたかも映画の世界に没頭しているかのようなものなんじゃないでしょうか。
だから、少しそのように頭の片隅に置いてもらうことで、没頭しすぎて苦しいという風に思っている人たちも、一歩引くことで、少し気持ちが楽になるんじゃないかなという風に思ったんですね。
知覚を通してしか、我々人間というのは世界を理解できないですよね。おそらくその五感によって作られた概念で世界を自分の中で構築する、という仕組みになっていると思うんですよ。
今の超ひも理論によれば、周波数による微妙な振動によって世界が作られているということですね。だとしたら、そこが1つの突破口で、我々の脳を通して知覚するいろんな可能性が広がっている、ということをおそらくおっしゃりたいと思うんですよね 。
そしてそういう三次元的な物の見方の方が、脳がただ五感があってというところだけで止まっているよりも、すごく進歩的だと思うんですが・・・。
●脳は絶え間なく振動する世界の受信機
結論を言うと、脳というのは、言ってみれば受信機みたいなものかなと思ったんですよ。この世界の絶え間なく振動する世界を受信する受信機です。
そうすると受信機とは何かと言うと、物を受容するということですよね。
受信するだけではなくて、自分で世界を変えるクリエート側にもなることができるんでしょうか?
もしそれがあったとしたら、すごくもっと違う可能性も出てくるかと思っているんですけれども、CHIECO先生はそこらへんはどう思われますか?
そうですね、面白い観点をありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、世界が周波数でできているとしたら、その周波数を変えるだけで 現実も変わるということですから、そういう考え方も生まれてきますし、だから私たちは現実を変えることができるんだ、という可能性は大いにあるかと思います。
ありがとうございます。
では、そろそろまとめに入らせていただきます。
CHIECOさんが、心理学の臨床実験を通してされてきたことというのが、我々は目という視覚ではないところの、触覚によっても色を感じ取ることができるのではないかということです。それはロドプシンという光を感じる物質があるから、という話です。
そしてそういう風に、実は我々が思っている以上に、人間の脳を始めとする生物学的な神経というのは、すごく柔軟性があり、可能性があるということです。
考えてみたらそうですよね。
どんな人間でも、最初の受精卵の細胞は1個から始まりますからね。1 個の細胞が分裂して、何十兆もの細胞に分化するとしたら、その大元の部分は同じ性質を持っているわけですから。
それで、おそらく五感の連携というものも取れるということなのでしょうね。
それを翻って考えた時に、先ほどの感覚と知覚の隔たりの話になりますが・・・。物を感じ取るという能力と、それを理解するという能力は別のものであるということですね。脳は知覚を司っているということでしたか?
脳が知覚を司っているということですね。
先ほど面白いことをおっしゃっていただいたと思うんですが、我々は最初1つの細胞だった。それが分化していって手になり、足になり、脳になり・・・という風にしていくんだと。
そして1度分化して手になってしまったものは、確かに普通にしていたら足にはならないんですけれども、脳の中で1回ポジションが決まっていても、後から何かの欠損が起こった場合、例えば左脳の一部が怪我をしてしまってそこが損傷したとしても、他の部分がそこが元担っていた機能を、補うように機能してくれるということがあります。
つまり脳の中で、分化をもう1回するような過程をしてくれるんですね。それを脳の可塑性と言いますが、ある程度人間の体というのは、そういった可塑性があるという風に言えるんですね。まさにそのことをおっしゃっていただいたと思います。
また、私たちの体そのものがまるでラジオの機械のように、電波をキャッチするものである。そしてそれを音に変換するのは私たちの体であるというような考え方のことをおっしゃっていただいたのかなと思って、確かにそうですよね。
そうですね。
2020年代に入って、AIというものがすごく進化してきて、人々の生活の中にも、色々なところの分野でそれが幅を利かせてくるようになりました。
そうすると例えば将棋だったら、もうAI の方が人間よりも完全に上なんですよね。
けれども、じゃあ人間は劣っているからAI よりも下なのかというと、全然そんなことはなくて、実は脳が最も得意とするものは、この世界を受容すること。見ること。
この世界を見ている観客を見ることができる、ということではないかなという風に思ったんですよね。
まさしく映画「マトリックス」がそうですよね。
AI にたくさんの人間がつながれていて、人間が感情でそれを見渡せる。見るということの集合としての世界があるという感覚ですね。良し悪しは別として。
だとしたらおそらく先ほどの超ひも理論ですね。周波数によって世界が構築されていて、それを脳が受信するというのが、実は突き詰めたら、最先端の科学では結論がそういう風な方向になっていく、ということでしょうか。
そうですね。
ありがとうございます。綺麗にまとめていただいて。
超ひも理論というその物理的な仮説を、生理学で説明するとしたらこんな感じです。ここまでが説明できるんじゃないでしょうか。というのを提唱させていただいたそのような実験でもあるかと思います。
面白いですね。
実験理学のお立場で、例えば認知心理学とかもそうでしょうけれども、そのお立場でこの結論に持っていかれる人というのが、感覚としてどのくらいいらっしゃるんでしょうか?
皆さんそういう風にトップを走っておられる方は、今の超ひも理論というところをやはり見据えて研究されているものなんでしょうか?
あまり同じような研究をされている方をお見かけしていなくて、私はどちらかというと異端かもしれません。
それを聞いて何か少し安心しました。
そうですか?
全員がこうだと少し怖いですか?
世の中の常識を打ち破る人は、大体異端から発しますよね。何にしてもですね。
時代の異端児こそが、世の中を切り開いていくんだと思うので、これは素晴らしいことだと思います。
ありがとうございます。異端児です。
名誉なことです。
また、次回に話をつなげていきたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
●さいごに
ありがとうございました。
物理のスリット実験では、観察者がいる時といない時で結果が変わる、ということが示されています。
つまり現実とは、実は曖昧なものとも言えるのかもしれません。あたかも映画マトリックスのように、脳がこの世界をそれぞれ独自に変換しているとも考えられ、それに一喜一憂している私たちは、あたかもそれぞれの映画に没頭しているかのようだと思いました。
あまり現実に没頭しすぎず、適度に俯瞰して過ごしてみる。あるいは異なる角度で見てみることで、もう少し気楽に人生を送ることができるようになるのではと思います。
また今回の手で色を知覚する実験により、自分はこれだけしかできないと限界を決めつけてしまうのではなく、ご自身の可能性を広げることで、より楽しい人生を送ることができるかもしれないということをご提案したいと思います。